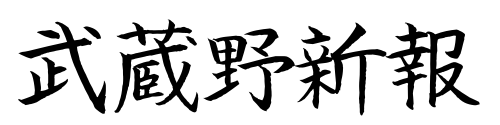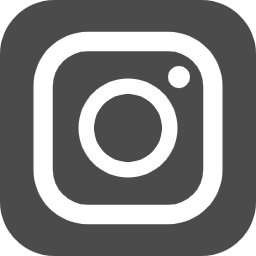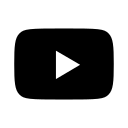こんばんは。
引き続き奥秩父の見所をご紹介してまいります。
今回は皆さまお待ちかねのあのスポットですよ!
行列必至のパワースポット
狼が待つ三ツ鳥居
三峰ビジターセンターの見学を終え、いよいよ三峯神社の境内へと入っていきます!
境内につながる道にはお土産物店などもあり、朝早くから参拝客を出迎えてくれています。
こうしてバス停から10分ほど歩くと、神社の鳥居が見えてきました。
この鳥居、他の神社とは異なり3つの鳥居が合わさった三ツ鳥居という変わった形をしているのが特徴的です。
そして鳥居の両端に建つこの狛犬のような動物。実はこれ、神社の守護神である狼なんです。
日本土着の狼で有名なニホンオオカミがこの近くに棲みついていたのですが、江戸時代には猪や盗賊から人々を守るものとして守護神に祀られたのだそう。
ちなみにこの秩父の地には絶滅したはずのニホンオオカミを見たという目撃情報もあるようですが、真相は果たして…。
神社の簡単な由来と歴史
同社の由来は、ヤマトタケルノミコトが東国へ遠征した際にこの地に立ち寄り、建国の神であるイザナミノミコトとイザナギノミコトを祀ってお宮を建てたことが始まりと言います。
本来三峰山とは妙法が岳(1332m)、白岩山(1921m)、雲取山(2017m)の3つの山の総称なのですが、これはヤマトタケルノミコトの父である景行天皇によって名付けられたもの。ちょうどヤマトタケルノミコトが巡った東国を巡行した際に、上総国でこれら3つの山が美しく連なることを聞いて三峰山と名付け、お宮は三峯宮と名付けられました。
その後修験道がもたらされるなど、神仏習合色を帯びた同社。鎌倉時代には三峯信仰が広まり、畠山重忠や新田義興など東国武士を中心に篤い信仰を受けました。ですが、1352年に新田氏らが足利氏との戦いに敗れて同社に身を潜めたことが足利氏の怒りにふれて、社領や社主を奪われた同社はその後140年にも渡って衰退しました。
ですが1503年から当山の荒廃を嘆いた修験者月観道満らによって、実に27年という長い歳月をかけて資金を募り同社の再建がなされました。
その後は聖護院派天台修験の関東総本山として隆盛を極めた同社は、明治時代の神仏分離によって今日の神社の形態になりました。
お寺のような随身門
鳥居から参道をしばらく歩くと左手に門が見えてきます。ここを通って本殿につながる拝殿へと向かうのが参拝のセオリーとなっています。
随神門と呼ばれるこちらの門は1691年にできたもの。
上記のように元は修験の場として名を馳せており、仏教色が強かったことから仁王門のような同門が建立されました。
現在の門は1965年に改修されたものであり、極彩色で彩られて往年の輝きを今に伝えています。
ちなみに明治時代までは本当に左右に仁王像が建っていましたが、これらの像は鴻巣の勝願寺に移されたのだそうです。
初詣はやはり混雑
そしていよいよ念願の拝殿へと参りました!拝殿へと繋がる階段を登っていきます。
しかし、県内屈指のパワースポットだけにこの混雑。山の上でまだ10時台というのに自家用車で来たと思しき人々が多く並んでいました。
しかし私も負けていられない。財布から5円玉を取り出し5分ほど並んで参拝することにしました。
お賽銭を入れて埼玉地域のますますの発展、そして大宮アルディージャのJ1復帰を祈って参りました。
どうか叶いますように。
ちなみに拝殿の格子には鮮やかな極彩色で描かれた彫刻で装飾されており、あたかも熊谷の聖天山歓喜院を思わせるような雰囲気でした。
あちらも本来はお寺ですが、これも神仏習合時代の名残ということでしょうか。
樹齢800年のご神木
こうして拝殿での初詣を終えると、次に目に入ったのは拝殿前のそれはそれは高い木。
これは鎌倉時代に畠山重忠によって植えられたという、同社のご神木
樹齢800年を数えると言われるこのご神木からは、神社に霊気をもたらす気が発せられているといいます。
近くで幹に触れることもできますので、私も気を注入。身も心も力強くなった感じがしますね!