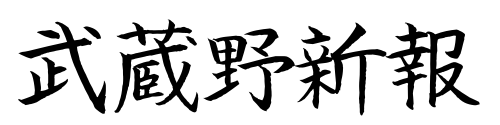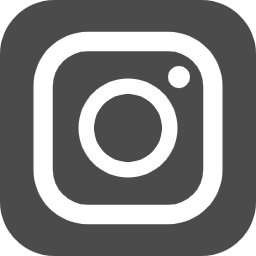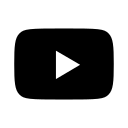こんばんは。大宮以外の埼玉・ふじみ野市編の第2回でございます。
今回からふじみ野市内のみどころをたくさんご紹介してまいりますよ〜。
ふじみ野市にアレが停車?
あの街と由来は同じ
 こちらがふじみ野市唯一の鉄道駅にして中心駅である、東武東上線の上福岡駅。
こちらがふじみ野市唯一の鉄道駅にして中心駅である、東武東上線の上福岡駅。
前回もお話ししたように、ふじみ野駅があるのはお隣の富士見市なんですよ。
この辺りは2005年までは上福岡市という市でしたが、この上福岡とはこの地にもともとあった「福岡町」だったことから付けられたもの。
博多天神の福岡との混同を避けるために「上」を付けたのだそうです。
ちなみにふじみ野や川越からさらに北の東松山市も、同じようにその名がつけられたのは言うまでもありません。
市民の憩いの場・福岡中央公園
 そんな上福岡駅から東に5分ほど歩いた場所にあるのが福岡中央公園です。
そんな上福岡駅から東に5分ほど歩いた場所にあるのが福岡中央公園です。
 1967年に周辺の団地造成に合わせて開園した同園。春には桜が咲き夏には涼しげな噴水が湧き上がり、日々市民の憩いの場となっている公園です。
1967年に周辺の団地造成に合わせて開園した同園。春には桜が咲き夏には涼しげな噴水が湧き上がり、日々市民の憩いの場となっている公園です。
そんな同園では様々なイベントの会場となっており、春の桜まつりや夏の上福岡七夕祭り、そして毎年11月の文化の日に開催されるふじみ野市産業まつりなどが開催されています。
新手のシンカリオン!?
紅葉の見頃は下旬くらいになりそうだな〜なんて考えながら園内を歩いていると、右手に見える緑と白のあのカラーリングはもしや…。
いいえ、これは残念ながら防災倉庫です。
元はトイレとして利用されていたのを防災倉庫へと流用したのだそう。
しかし前面の窓にちゃんとガラスがはめ込まれていたりと、なかなか本格的ですよ!
あ、念のため言っておきますけどふじみ野市に新幹線は走っていませんよ〜。
スポット紹介
◇福岡中央公園
- 住所:埼玉県ふじみ野市上野台1-4
新たなショッピングスポット誕生?
そして公園から3分ほど北に進むと、採用試験やふるさと納税が話題のふじみ野市役所があります。ガラス張りでオシャレですね〜!
そして市役所の北側に見えてくるこの広大な空き地。
日本無線の工場があった場所ということですが…、
 なんとイオンタウンふじみ野が建設される予定(完成時期未定)なのだということ。
なんとイオンタウンふじみ野が建設される予定(完成時期未定)なのだということ。
すぐ隣にイトーヨーカドーがあるのが気がかりではあるのですが、地上5階地下1階になるというこのイオンが完成すると、新たなヒトやモノの流れが生まれることでしょうね。
往時を偲ばせる船問屋
江戸と川越を結ぶ新河岸舟運
 そして駅から北に約1.7km。川越市との市境に流れる新河岸川までやってきました。
そして駅から北に約1.7km。川越市との市境に流れる新河岸川までやってきました。
 この新河岸川では江戸幕府が成立した江戸時代から東京遷都を経て昭和時代初期まで、首都東京と江戸の母と呼ばれた川越の間で物資を輸送する舟運が盛んに行われていました。
この新河岸川では江戸幕府が成立した江戸時代から東京遷都を経て昭和時代初期まで、首都東京と江戸の母と呼ばれた川越の間で物資を輸送する舟運が盛んに行われていました。
福岡河岸と名付けられたこの地からも多くの物資が川を伝って運ばれており、川の沿岸には船着き場も残されています。
ふじみ野市にも時の鐘?
そしてそんな船着き場の近くに、なんだか川越の時の鐘のような古めかしくて小高い建物が見えるぞ。
 近づいてみると、昔ながらの石畳の道でなんだか江戸時代にタイムスリップしたようだ。
近づいてみると、昔ながらの石畳の道でなんだか江戸時代にタイムスリップしたようだ。
そうして見えてくるのが、ふじみ野市立福岡河岸記念館です。
果たして一体ここはどんな施設なんだ?
舟運の歴史を伝える資料館
 正面の案内によると、ここは江戸時代後期から明治末期までこの地で舟運を営んでいた船問屋「福田屋」の建物を譲り受けた資料館。
正面の案内によると、ここは江戸時代後期から明治末期までこの地で舟運を営んでいた船問屋「福田屋」の建物を譲り受けた資料館。
2011年には埼玉県内ではじめて景観重要建造物に指定されました。
後述するように入館料を払って敷地内へ。
現役時代は武道場など多くの建物があったそうですが、現在はそのうち主屋と台所、文庫蔵に3階建ての離れが残されています。
建物も庭園も綺麗に手入れされていて、往時の雰囲気がひしひしと伝わってきます。
問屋の顔・主屋の帳場
まずは明治初期に建てられた2階建ての主屋から見ていきましょう。靴を脱いでお邪魔します!
すると目に入ってくるのが、この荷車に荷物を受ける帳場。
帳場机や銭箱やそろばんが置かれて荷主との取引が行われており、いわば問屋の顔とも呼ばれる場所でした。
今でもそろばんを弾く音が聞こえてきそうだ…。
200年の歴史を有する舟運
そして帳場隣の土間には、舟運に使われていた船や福岡河岸での舟運についてのパネル展示があります。
 新河岸川での舟運は、1638年に焼失した川越の仙波東照宮の再建資材を運んだのが始まりとされています。
新河岸川での舟運は、1638年に焼失した川越の仙波東照宮の再建資材を運んだのが始まりとされています。
ここ福岡河岸では、1733年頃から村人が農業のかたわら回漕業を営んだのが始まりとされています。この福田屋の他に江戸屋や吉野屋という3軒の問屋が回漕業を営み、周辺農家の農産物を江戸に運んでいました。
1831年には福田屋の七代目仙蔵が船問屋を開き、肥料や灰などを江戸の地に運んで行ったといいます。
しかし明治時代に入った1895年に国分寺〜川越を結ぶ川越鉄道(西武新宿線の前身)が開通すると、吉野屋以外の船問屋は回漕業を縮小し、明治末期には福田屋と江戸屋が回漕業から撤退、吉野屋だけが大正末期まで船問屋として営業を続けました。
その後大水害を契機として1920年から新河岸川の改修工事が始まり、続く1931年には通船停止令が出され、ついに舟運は過去のものになってしまったというわけです。
栄華を示すお台所
時代とともに衰退した舟運ですが、栄華を極めたことは事実。
その証拠に明治初期に主屋とともに設けられた台所は非常に広々としており、客人をもてなすため多くの料理が作られていたことが伺えます。
 ちなみに福田屋の主人や従業員は主屋の2階で寝泊りをしていたのですが、こちらの2階は残念ながら普段は公開していないとのこと。
ちなみに福田屋の主人や従業員は主屋の2階で寝泊りをしていたのですが、こちらの2階は残念ながら普段は公開していないとのこと。
それでも舟運が最盛期を迎えた頃にできたこの主屋は非常に広々とした作りになっていて、その盛況を感じさせます。
東上線ができたのもこの人のおかげ
星野真里のご先祖様
こちらでは福田屋で用いられた食器や備品などがたくさん展示されています。
そんな中にある人物の肖像画。
この人物は福田屋の10代目星野仙蔵(1870〜1917)。埼玉県会議員や衆議院議員も務めましたが、なんとふじみ野出身の女優・星野真里さんのご先祖様なのだそう!
東上鉄道の建設に尽力
そんな彼が残した功績といえば、何と言っても東上線の前身である東上鉄道の設立。
東武鉄道の初代社長を務めた根津嘉一郎とともに、地元財界の有力者として東上鉄道の敷設に尽力しました。
鉄道や河川改修などで家業である舟運の衰退も見込まれましたが、1914年に池袋〜田面沢間が無事開通。仙蔵は地元出身者として同社の監査役となりました。
ちなみに以前もお話ししたように、東上という名前は東京と上州渋川を結ぼうとしていたことからその名がついたんですよ。
趣向を凝らした3階建の離れ
 そして同じく仙蔵の功績は、河岸から見えた3階建の離れを建てたこと。
そして同じく仙蔵の功績は、河岸から見えた3階建の離れを建てたこと。
接客用に1900年ごろに建てたといいます。
この離れは3階まで届く通し柱が6本建てられており、このおかげで関東大震災の際にもビクともしなかったのだとか。
3階建の建物には全ての階に床の間が作られており、特に2階には生前剣道を嗜んだ仙蔵らしく亀の剣道試合や剣道防具の透かし彫りが施された欄間があるなど、独創性あふれる作りになっています。
ただ、施設の都合上普段の見学は1階までで上層階は非公開。
なのですが、来たる12/2(土)と1/19(土)に特別公開を行う予定です。
見学には上福岡歴史民俗資料館宛に予約が必要となりますので、お早めにどうぞ!
そんな福岡河岸記念館ですが、上福岡地域にはまだまだたくさんのみどころがあります。
次回もサービスサービスぅ!
つづく
スポット紹介
◇福岡河岸記念館
- 住所:埼玉県ふじみ野市福岡3-4-2
- 電話番号:049-269-4859
- 開館時間:10:00〜16:00/16:30(5~9月)
- 休館日:月曜日(祝日にあたるときも休館),12/27~1/4
- 入館料:小中高生¥50/大人¥100 (20人以上の団体は1人¥80)
- 備考:離れの2・3階は年数回公開日あり、上福岡歴史民族資料館宛に要予約(049-261−6065)