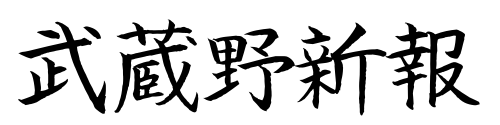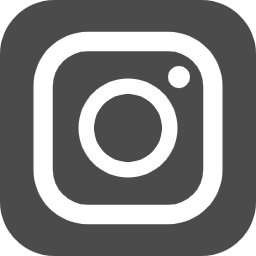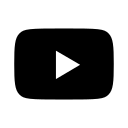岩槻人形博物館の開館に合わせて、前回は地元岩槻の人形店2社に話を聞いた。
埼玉県内では岩槻以外にも雛人形の産地があるが、他の産地では同館の開館をどのように見るか。
そのうちの一つ、所沢市にある秋月 小寺人形を訪ねた。
所沢人形について
その歴史

(ちょこたび埼玉より)
所沢周辺では、江戸末期の天保年間に3軒の業者によって始められたとされている。当初は農家の副業として始められ、岩槻と並び県内有数の産地である鴻巣の職人が作り方を教えたという。
その後産業として発展を続け、着付けを得意とする業者がいくつも出てきた。
手作業を主としてきた人形づくりも第二次ベビーブームの1970年代頃には量産化で最盛期を迎えた。しかし、近年では後継者不足や問屋都合で店を畳む人形店も見られる。
雛人形にまつわる地域行事
それでも所沢人形協会を中心に、産業振興や文化継承が図られている。
同会には所沢をはじめ新座やふじみ野、さらに東大和など都内の周辺人形店も名を連ねる。

(野老澤造商店HPより)
雛人形にまつわる地域行事も多い。3/8(日)まで市内の野老澤造商店では江戸後期から平成までに作られた雛人形を飾る野老澤雛物語が開催されている。
加えて所澤神明社では毎年6月になると人形供養祭が執り行われ、3,000体近い人形を供養する。
手作業を貫く、日本一小さい人形店
第一線で活躍する匠
今回は所沢駅東口から歩いて5分ほどの場所にある秋月 小寺人形を訪ねた。雛人形はもちろん五月人形や鯉のぼりなども扱う。
周辺の工房で機械生産が進められている中、1927年創業の同店では創業以来の手作業による人形作りを貫いている。
同店を切り盛りするのが、同地で人形製作を行うこと50年超の小寺香氏。
熟練の技術を基に芯の削り出しや整形など、人形製作にかかる全ての工程を自身の腕で行なっている。一生に一度購入することの多い商品だけに手を抜くことは許されない。それゆえ手を込めることが何よりも重要ということで手作りにこだわる。
その腕はまさに一級で、1994年には県の伝統工芸士として認定されている。
人形製作だけでなく、70歳近い現在でも接客や配送などもこなす。ひな祭りシーズンが近いだけに訪問時にも多くの来客があったが、自身の経験を基にお客にとって最適な雛人形を提案していた。
「他の店と違って、うちは製作から販売まで1店舗でこなす日本一小さい人形店」と同氏は称する。
帯から生まれる雛人形
そんな同店で一際注目を集めているのが、着物の帯から作る雛人形だ。昔着ていた着物の帯などを雛人形の衣装に仕立て上げる。
元は得意客との会話から生まれたというが、現在では本来の商圏である所沢周辺はもちろん、北は北海道、南は沖縄まで全国から同品製作の依頼がある。それだけでなく他の人形店からも取り扱いの相談があるという。
同店に限らず少子化などの影響で雛人形を取り巻く市場も変化しつつあるが、2回目・3回目の成人式として大人になってから買い求める女性も多い。そのような客の声にも対応しうるサービスといえよう。
人形作りの魅力とは?
このような同店の特徴ある人形作りを行う同氏は、新聞やテレビなどで取り上げられることも多い。
本題から少しずれるが、同氏に人形作りの魅力について聞いた。
特にお客の笑顔やおめでたい瞬間に立ち会えることが人形作りの魅力と同氏は語る。
以前、同氏の元に24歳で亡くなった女性の母親から成人式で着ていた振袖の帯で人形を作って欲しいという依頼があった。実際に作った雛人形は女性の仏壇の前に飾ってあるということで、依頼者の喜びに繋げることができたという。
また東日本大震災で被災した一家からは、大災害の中で唯一残った着物の帯で人形を作って欲しいという依頼もあったそうだ。
女子の健やかな成長を祝うという本来の目的はもちろん、人生の様々な場面で人々に喜びを与えるのが雛人形で、それを作り出せることこそが大きな魅力なのだろう。