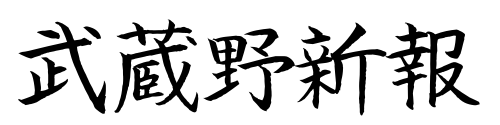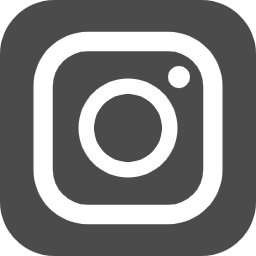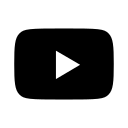江戸時代に日光街道四番目の宿場町・粕壁宿として栄えた春日部市。
400年以上経った今でも、街中には当時の面影が残る。
粕壁宿とは
江戸時代に日光東照宮が築かれると、江戸・日本橋を基点に日光へ至る日光街道が設けられた。
同街道で千住・草加・越谷に続く4番目の宿場町として設けられたのが、同宿にあたる。日本橋より9里2町(約36km)の距離に位置しており、歩いてほぼ一日かかる距離だったという。
同宿は、現在の春日部駅東口に東西に走る春日部大通りにあたる。南北10町25間(約1.1km)にわたる広さとなっていた同宿には、江戸後期の天保年間には本陣1軒・脇本陣1軒・旅籠45軒・問屋場1ヶ所・家773軒の規模で、日光街道23宿のうちの6番目を誇った。
春日部重行眠る真言宗最勝院
同宿の上手にあたる日光側には、多くの寺院が並ぶことから寺町と呼ばれ往年の雰囲気を色濃く残す。
その中の真言宗最勝院は、後述する春日部重行の墳丘があることで知られる。
明治時代には粕壁小学校や税務署が設けられ、地域初の鉄道である千住馬車鉄道の起点になるなど、地域におけるまちづくりの拠点になっていた。
同寺境内には南北朝時代の武将・春日部重行(1294-1336)が埋葬されているという墳丘がある。
新田義貞に仕えた重行は天皇を護衛し、鎌倉幕府を打倒した後醍醐天皇の建武の新政を支持。新田軍として各地で旧幕府軍と戦った。
しかし同年6月30日に北朝側の足利尊氏軍と京都で戦うが、敗戦し自害した。その遺骨を長男の家縄が同地に持ち帰り、同寺へ埋葬したという。
重行の偉業をたたえ、地域では毎年ゴールデンウィークに春日部重行公祭が行われている。
蔵残る街道を歩く
同宿を受け継ぐ春日部大通りを歩いて行く。
街道沿いには青物店や穀物店や飲食店などが建ち並び、上手側では4と9のつく日には六斎市が開かれていた。古利根川を通じて、江戸からの結んだ物資も多数集まっていた。
宿場町の住民には人馬を負担する義務があったが、その代わりに年貢一万坪分が免除されていたという。
黒塗の土蔵ー浜島家住宅土蔵
そのような同通り沿いには往年の雰囲気を残す建造物も多い。
浜島家住宅土蔵もその一つだ。
明治期に入ってから建てられたとされ、米問屋の蔵として利用されてきた同蔵。外壁を黒漆喰塗として鬼瓦に影盛を施すなど関東の土蔵造の特徴を示している。
同宿商家の数少ない遺構で往事の面影を伝える大型土蔵として、2015年には国の重要文化財に指定されている。
力持ちの石 東八幡神社
同宿の入口にあたる南側へ至る。
その近隣にあるのが東八幡神社だ。
ホンダワケノミコトを祀る同社は京都・男山に鎮座する石清水八幡宮から分祀を受けたとされ、家内安全や商売繁盛などに利益があるとされる。
樹齢600年を迎える神木の大ケヤキや稲荷神社といった合祀社などがある境内で、一際目を引くのが安置されている大きな石。
これは江戸後期の興行師・三之宮卯之助(1806〜1854)が持ち上げたとされるもの。越谷三之宮に生を受けた卯之助は、生まれつきは小柄で虚弱体質であったが一念発起し猛練習に励み、江戸を代表する力持ちとなった。
やがて力自慢の者を集めて力持ちの興行をはじめ、馬に乗った人を乗せた舟ごと持ち上げる「人馬舟持ち上げ」で日本一の力持ちとして全国にその名を馳せた。
地元越谷をはじめ三之宮が持ち上げたとされる巨石は全国各地に残るが、これは1832年に持ち上げたとされるものでその重さは百貫(375kg)に上るとされる。