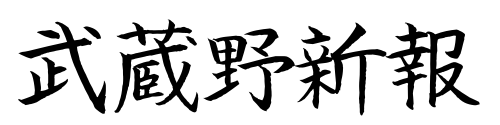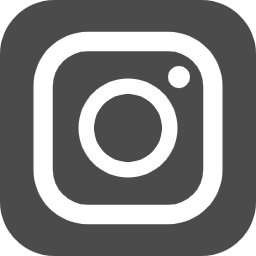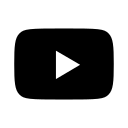さいたま市議会では12月定例会が11/27〜12/20の会期で実施されております。
先週12/2〜4にかけて各議員による一般質問が行われました。その中で気になった答弁をピックアップしてご紹介します。
放課後児童クラブの充実について
まずは出雲圭子議員(民主改革)からの放課後児童クラブに関する質問2点です。
まちづくりから考える放課後児童クラブの増設の必要性について
北側の区画整理が終わった西区には新しい家族が多く住み始めており、西大宮地域だけでもこの1年で1,700人も人口が増えています。
しかし共働き世帯が想像以上に増加したにも関わらず、同地区には市有地が少ないため放課後児童クラブをあまり建てられない現実があります。
同地区の小学校が同クラブへの入会希望アンケートを取ったところ、50人が新規入会を希望していました。それでも既存のクラブはどこも定員増でこの50人を受け入れられません。
今後もこのような希望者が減ることは考えにくい状況です。
保護者の間でも新規設置を目指す動きがあるが、用地転用の関係でなかなか進んでいません。
子どもたちの生活環境向上のためにも、新規設置は必要と同議員は考えます。
なおかつ市長の掲げる「子育て楽しいまちづくり」のためにも、まちづくりの観点からこの状況を変えて行く必要があるとしています。
2009年に施行された「大規模共同住宅の建設における子育て支援施設の設置に関する要綱」では、300戸以上の共同住宅を建てる事業者に対し事前に同施設の設置に関する事前協議を求めています。それでも施行以後認可外保育園2園の設置に留ま理、同クラブの設置には至っていません。
市でも対象となる大規模共同住宅に対して同施設の設置を義務化するよう取り組んでいくと昨年9月に答弁があったが、どのような検討や制度設計がなされたか聞きます。
質問への回答
金子子ども未来局長からの回答です。

同局では小学校区ごとに児童数の推移や既存施設の利用状況から利用ニーズを把握し、既存施設で充足できない場合には民間児童クラブを活用してできる限り受け皿を広げています。
西大宮地域では確かに宅地開発によって急激に人口が増えています。
教育委員会からもこの地域の小学校の児童数の推移を聞き、来年度以降もニーズの増加を見込んでいます。
こうしたことから利用者数の推移から来年度以降のニーズに対応できるよう、受け入れ枠の拡大や新規増設も含めて運営事業者と協議を行っているところです。
なお同地区は区画整理中で既存の賃貸物件が少ないことから、土地権利者の土地利用に関する意向を受けた際には運営事業者に情報提供を行うなど、市としても支援を行っています。
今後もまちづくりに携われる部署や機関と連携しながら、市としても同施設のニーズを的確に掴んでいきたいとしています。
大規模住宅への設置義務化についても関係部署と検討を行っていますが、具体的な取り組み状況については「検討中」としています。
夏休みや雨の日の放課後児童クラブの過ごし方について
同議員は続けて、夏休みや雨の日の同クラブでの過ごし方について質問もしています。
近年30度以上の真夏日が続くことで、そのような日には外遊びは原則として禁止でクーラーの設置してある施設内で過ごすことになります。
雨の日も同様に外遊びができません。
それでも定員数も逼迫している市内の児童クラブでは、このような時には非常に窮屈な思いをさせています。
学校の空き教室や体育館を解放しゆとりのある時間を過ごせるようにできればいいのですが、児童クラブと学校の連携をどう改善していくか聞きます。
質問への回答
久保田副教育長からの回答です。
空き教室を活用した児童クラブの設置は教育委員会としても重要な課題です。子ども未来局と連携を図りながら増設を進めています。
校庭利用については、クラブからの要望があった場合学校との協議の上で一定のルールのもとで開放しています。
体育館や空き教室の利用は、学校運営に支障のない範囲で子ども未来局と連携して進めていきたいとしました。
あと半年間で夏休みですが、子ども未来局からの要望を受けた上で学校としても利用可能な教室等を提供できればとしています。
ケアラーへの支援について
稲川智美議員(自民真政)からはケアラー支援について2点質問がありました。
ケアラー支援条例の制定について
誰もが介護をしされる少子高齢化社会において、老老介護やヤングケアなど介護は多様化しています。
多重介護など新たな形態も出ているが、それに対応できるようケアラーへの支援が必要です。
市では包括支援センターでの介護者サロンを実施してきたが、ケアは日々新しい形態が生まれており次の段階に進むことが必要と考えられます。
介護殺人も多発しているからこそ、介護者が追い詰められている現実を理解することが重要です。
昨年の議会でもケアラー支援について研究をしていくと答弁があったが、どのように研究を行ったかを聞きます。
合わせて、市のしあわせ倍増プランの中でもケアラー支援をしっかり位置付け条例を定める方針で進んでいってほしいが、市の方向性を聞きます。
質問への回答
清水保険福祉局長からの回答です。
介護をするケアラーに対する支援は、彼らの明るい人生のためにも大変重要と認識しています。
市でも地域包括支援センターや市職員を対象に、介護者の様々な負担に対応できるよう研修を行い支援体制の強化に努めています。
ケアラー支援の研究については国や県の法律や条例を参照していますが、今後も支援充実に努めながら国や県・他の政令指定都市の状況を把握し、様々な課題を整理して条例制定の是非を検討したいとしています。
ヤングケアラーの支援について
同議員は続けて、ヤングケアラーの支援について質問もしています。
小中高校生が家族のケアを担い本来の学業や交友関係に支障をきたしているのがヤングケアラーです。
厚生労働省では要保護児童対策地域協議会(要対協)におけるヤングケアラーへの対策として通達を出しました。その中では全国の要対協でのヤングケアラーへの認知度が3割程度に止まっている一方、彼らの4割以上が1日5時間以上介護や世話を行っており3割近く以上が学校に行けていないとありました。
こうしたことから市でもヤングケアラーの実態把握に努めその支援にあたるべきと考えますが、市の見解を聞きます。
質問への回答
金子子ども未来局長からの回答です。

先の通達にもあったように要対協自体での認知度が低かったことから、まずは関係各者がヤングケアラーの概念について認識し適切な対応を取ることが必要とされています。
国ではこうした子どもや家庭を把握するアセスメントツールを開発する予定です。その結果を踏まえどのように実態調査を行うか精査し、協力機関を通じた調査などを検討したいとしています。
合わせて虐待により保護や支援が必要な子どもに対してもヤングケアラーであるという視点を持ち、家事援助や障害福祉サービスなど適切な支援に繋げれられるよう関係部局と連携を図りたいとしています。
防災・減災について
土橋勇司議員(自民さいたま市議団)からは防災・減災に関する質問が2点ありました。
さいたま市総合防災訓練について
10月の台風19号ではさいたま市内でも誕生以来の大きな被害がありました。環境変化を考えると豪雨災害はこれまで以上に危険度が高くなっています。
それゆえ、今まで以上に防災・減災の取り組みが必要になってくるのは明白と言えます。
さいたま市でも年に一度総合防災訓練を実施しているものの、これまでは地震を対象にしていると同議員は認識しています。
今回の台風を考えると、水害に関しても意識して訓練を実施すべきと考えます。
これについて市の見解を問います。
質問への回答
清水勇人市長から回答がありました。

近年毎年のように国内で大規模水害が発生していることから、今年度の防災訓練では市民に水害に対する知識や意識を深めてもらうために水防訓練や水難救助訓練を新たに実施しています。
特に洪水時のドアにかかる圧力の体験や水流がある中での歩行体験ができる水災害体験装置を導入しています。他にも水害時にいち早く避難ができるよう、浸水防災マップやハザードマップの配布・展示も実施しました。
来年度の訓練は会場・内容とも検討中ですが、今回の災害を受けて市民により水害に対してこれまで以上備えができるよう訓練内容を見直す必要があると考えています。
それゆえこれまでの訓練に加えて広域避難の周知など、災害発生から避難所の運営まで一連の流れを体験できる住民参加型の訓練を想定しています。
なお各区でも訓練を行なっていますが、特に河川がある区については訓練を強化する必要があり総合防災訓練とともに強化を行いたいとしています。
引き続き市民の安全・財産を守る防災・減災に市としても取り組んでいくと締めました。
災害に対する意識と知識の向上について
あわせて同議員からは以下の質問がありました。
さいたま市では数多くのハザードマップや防災資料が配布されていますが、あまりにも数が多すぎるためどれが自分に最適なのかがわかりづらいと長年感じています。
一度は目を通してもらえて、見やすくわかりやすく記憶に残り、何より災害時に役に立つものとすべきと考えていますが、市としてはどのように取り組んでいるかを聞きます
今回の台風では区ごとでも災害状況が異なっていたましたが、様々な範囲をカバーしうる地域ごとの防災ガイドブックの作成も喫緊に検討すべきと考えます。それに関する見解も合わせて聞きます。
質問への回答
山崎総務局長からの回答です。

2015年に市では防災ガイドブックを作成しましたが、以後様々な災害や法改正が生じてきたため現在新たな防災ガイドブックを作成している段階です。
作成にあたっては有識者や関係団体から助言を受けており、災害に対する意識や知識の向上に寄与しうるよう見やすく読みやすいものにしていきます。
また地域全体を包括できるよう、地震や風水害など災害の種類に応じた構成にしてあります。
加えて防災情報を細かく市民に周知すべく、それぞれの説明部分にQRコードを設け市HP内の情報に誘導できるほか音声読み上げコードも掲載します。
なお区ごとのブックについては、地域区分の観点から他の政令市の事例や観点を踏まえつつ今後検討していくとしています。