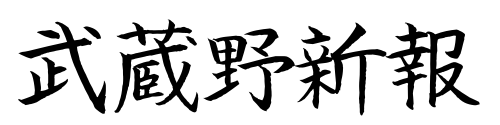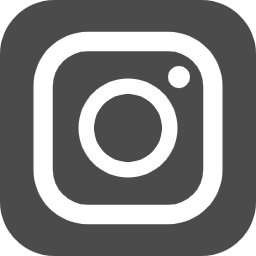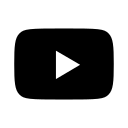先日ですがさいたま市内で歴史上大きな価値があるものが見つかり、本日より公開が始まりました。
遺跡から見つかった古銭
10日ほど前になりますが、こんな出来事がさいたま市内でありました。
さいたま市教育委員会は20日、古代の集落遺跡「与野西遺跡」(さいたま市中央区桜丘1)から、流通貨幣「和同開珎(わどうかいちん)」2枚が出土したと発表した。埼玉県内ではこれまで、秩父市や川越市など8遺跡から8枚が発見されており、今回が9、10例目。
〜中略〜
見つかった銅銭はいずれも直径約2.4センチ、中央に1辺0.7センチの正方形の穴が開いている円形方孔で、表面には時計回りに「和同開珎」と刻まれている。奈良後期~平安初期の竪穴式住居跡から発見された。発見場所は、当時の武蔵国足立郡の郡衙(ぐんが)(役場)から北東1キロ付近に位置するという。
〜中略〜
市立博物館で6月4~16日、発見された2枚を公開する。入場無料。【鷲頭彰子】
(「『和同開珎』2枚が出土 さいたま市『与野西遺跡』」 2019/5/21 毎日新聞)
現在発掘が進められている与野西遺跡内で、古銭・和同開珎が2枚見つかりました。
これまで秩父や川越など埼玉県内では8枚発見されていますが、さいたま市内で発見されたのはこれが初めてです。
後述するように日本初の本格的な流通貨幣として知られる同銭ですが、実は埼玉のある場所と大きな関わりがあるのです。
埼玉に関わりのある古銭
日本初の流通貨幣
歴史の授業で習ったという方が多いとは思いますが、改めて和同開珎がなんたるかをご説明します。
和同開珎は奈良時代直前の708年に発行が始まった貨幣です。直径24mmほどの円形で中央には一辺約7mmの正方形の穴が開けられ、「和同開珎」の文字があしらわれているのが特徴です。
そして同銭の最大の特徴は日本初の流通貨幣であること。それまでも富本銭などの貨幣が発行されてはいましたが、それほど流通しなかったと言われています。
しかし同銭の発行が始まると、政府も給与の貨幣支給を奨励したり貨幣を蓄えた者の位を上げる蓄銭叙位令(711年)などを施行し、それまで物々交換が主流であった日本社会での貨幣流通を目論みました。
それが功を奏して主に都があった畿内周辺で流通がなされるようになります。
その後私鋳銭が蔓延したことから760年に同銭の10倍の価値のある万年通宝の発行に舵を切りました。それでも同銭はその後9世紀中頃まで流通していたといいます。
元号まで変わった和銅の衝撃
そしてこの和同開珎の発行のきっかけとなった場所が、秩父市黒谷にある和銅遺跡です!
続日本紀によると、元明天皇の代にこの地より自然銅が発見され708年の正月に朝廷に献上されました。
元明天皇はこれに大いに喜び、なんとその日のうちに元号を「和銅」に改元したといいます。
そうして同銭が発行されるに至ったのですが、同遺跡の銅も当然使用されました。
ちなみに同銭が使用されていたのは主に関西で6000例近く発掘されていますが、埼玉で発掘されたものについては富の象徴としてお守りとして使われていた可能性があるようです。
スポット紹介
◇和銅遺跡
- 住所:埼玉県秩父市黒谷1918